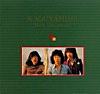最近、ちょっとした思いつきで「日本の実力派女性シンガー(個人的見解)」プレイリストを作りはじめた。
そこには、「竹内まりや」や「中島みゆき」から、「aiko」「SHISHAMO」「AI」「JUJU」「MISIA」まで混ざっていたりする。
で、そのなかに「あいみょん」も当然入ってきて、気がつくと生活のなかに、呼吸のように彼女の曲が溶け込んでいた。
ふと耳に留まったのが『ポプリの葉』という曲。
代表曲『君はロックなんて聞かない』ではなく、この地味めの一曲を引っかけてしまうあたり、たぶんオレの性分なんだろう。
勝手に解釈して掘り下げてみる。
「あいみょんファン」の方々に怒られるのを覚悟しながら。
🎼 🌿 🥀 🌿 🎼
「香り」は「存在理由」:「顔(存在)の理由=顔理」という裏読み
この曲のなかで象徴的に出てくるモチーフが「香り」だ。
ポプリ、という枯れた花の残り香を抱える感覚。
でもこれ、単なる嗅覚の描写に留まらない気がした。
そこでふと思ったのが、「香り」を「顔理」と裏読みすることだった。
つまり、「香り」は「顔(存在)の理由」なのではないか、という仮説。
夏目漱石が得意とした“語感から意味を揺さぶる言葉遊び”・・・
それに阿久悠が乗せた昭和歌謡の感性が、無意識のうちにこの詞にも流れているように思えてきた。
🎼 🌿 🥀 🌿 🎼
あいみょんの歌詞には、はっきりと「阿久悠的な仕掛け」が見える。
たとえば阿久悠の作詞では、「行けない」を「行かない」と言い換えるような心情のすり替えが多用された。
彼の詩は論理ではなく情緒で構築されており、夏目漱石的な言葉の“間”や余白が漂う。
『ポプリの葉』でも、「香りを抱えて家に帰る」ではなく、「香りの中で今日も眠る」という選択がなされている。
これは単なる回帰ではなく、記憶のなかで生きることを選んだ詩的表明だ。
あいみょんはまるで“夏目漱石的阿久悠”の再来のように感じる。
なので「作詞」ではなく「作詩」と表現したい。
🎼 🌿 🥀 🌿 🎼
ハーモニクスの歴史的引用:1970年代フォークとの対話
たとえば、かぐや姫の『22歳の別れ』を思い出してほしい。
AメロのラストEmの上で、最後に1・2・3弦12フレットのハーモニクスが儚く鳴る。
それは物語が切り替わる前の“覚悟のような沈黙”として配置されていた。
あいみょんは、その逆を行く。
『ポプリの葉』では、「香りの中で今日も眠る」という最後の言葉に、まさにそのハーモニクスを重ねるように響かせて終える。
つまり、70年代のフォーク詩人が“切り替わり”の合図として使った音を、彼女は“終わり”の証として使っているのだ。
偶然かもしれない。
でも、そうとは思いたくないほどの美しさが、そこにはある。
🎼 🌿 🥀 🌿 🎼
忘れられないものとしての「香り」
この曲のラスト、あいみょんはあえて「忘れる」とも「諦める」とも言わない。
彼女は「眠る」とだけ歌って、すべてを沈めてしまう。
香りという言葉に込められた、顔(存在)の理由を抱いたまま、そっと、静かに記憶のなかへと沈んでいく。
それは、「忘れられなかった」という事実の肯定であり、そしてそのまま“香りと共に沈んでいく”選択だ。
ここには「渡辺真知子」の「迷い道」冒頭における「現在・過去・未来」の「不自然な並べ方」とも共通する。
「今=現在」において「香り=過去」を抱いて「眠り」について、目覚める先には「未来」が待っている。
ここに「過去の自分と和解して、自己のアイデンティティを確立する」という構造が成り立ってくる。
🎼 🌿 🥀 🌿 🎼
あいみょんのオールナイトニッポンGOLDを偶然聞いて
6月6日の夜、それは偶然だった。
理由は覚えていないが、民放AMにチューニングを変えた時、あいみょんの声が流れてきた。
内容は覚えていない。
しかし、エンディング曲に「君はロックなんて聞かない」のフレーズが流れてきた。
そこで思った。
あいみょんがエンディングにこの曲を持ってきているのは、単なる「ヒット曲のアイコン的な利用」ではなく「ヒット曲をあえてエンディングに持ってくることによって『私は歌謡界(芸能界)に”利用”や”消化”なんてされない』とアンチテーゼを送っているのではないか」と。
🎼 🌿 🥀 🌿 🎼
あいみょんはやはり「聞かない」では済まされない
あいみょんは、意識してかせずか、フォークソングや昭和歌謡の”詩人”たちが遺した“音と言葉の余白”を確かに受け継いでいる。
阿久悠の“すり替え”、夏目漱石的“余白”、1970年代的“音の間(ま)”。
その全てが、『ポプリの葉』というさりげない楽曲に封じられていた。
だからあえて言いたい。
僕はあいみょんなんて聞かない・・・けれど、今日もまた、聴いてしまう。
そしてエンディングの「眠る」に重ねられたハーモニクスが心に残る
Kunverkisto Mainŝi-Ijoŭns
🎼 🌿 🥀 🌿 🎼
制作して参加しているグループ